実は、ワンオペ育児には見えない落とし穴があるのをご存じですか?こうした小さな我慢の積み重ねが、
気づけば、心身を削り取る育児地獄を作ってしまうんです…。でも安心してください。
私もそこでどん底を味わいましたが、あるきっかけで育児地獄から抜け出せるんです。

夫も実家も頼れない。夜泣きと不安で涙が止まらない…。

やっと我が子に会えて幸せなのに、なんでこんなに胸が苦しいんだろう。
もしかして、これが産後うつなの?

ワンオペ出産した他のママは一体どうやってるのかほんとに知りたい。
この記事では、ワンオペ出産後、不安と疑問で頭がいっぱいになるあなたの悩みを解決します。
ワンオペ出産って初めてだらけで、気が張って眠れないし、全然リラックスできない。
もちろん我が子は可愛いけど、そんな生活を続けていると、気づかないうちに少しづつストレスが溜まってしまうんです。
正直、ワンオペでの出産・育児は想像以上に過酷…。
私も出産直後、寝不足と孤独の中で「笑うことを忘れていた」時期がありました。
もちろん子どもは可愛いんだけど、やっぱり人に辛いって言えなくて、夜になると自分でも分からない涙が出てくるって、そんな日々を過ごしたこともあります。
でも大丈夫。
ワンオペ出産のあとの産後も、どう過ごしたらいいかを知ることで、不安も軽くなり、つらさを軽くなったんです。
この記事では、ワンオペ出産後に起こりやすい産後うつの7つのサインと、心が軽くなる乗り越え方・相談先を紹介します。
読めば、「あ、これ私だけじゃないんだ」って安心できるはず。
つらい気持ちをそのままにせず、あなたの心を守る一歩をここから始めましょう。
- 「ワンオペ出産」と産後うつの関係とは?3つの基本ポイント
- 「ワンオペ出産」で産後うつになりやすい人の5つの特徴とチェックリスト
- 「ワンオペ出産」でどん底に…産後うつを乗り越えた3人のママの体験談
- 「ワンオペ出産」中のママのための5つの乗り越え方
- 「ワンオペ出産」で悩むママのために、パートナーや家族が知っておくべき3つのこと
「ワンオペ出産」と産後うつの関係とは?3つの基本ポイント
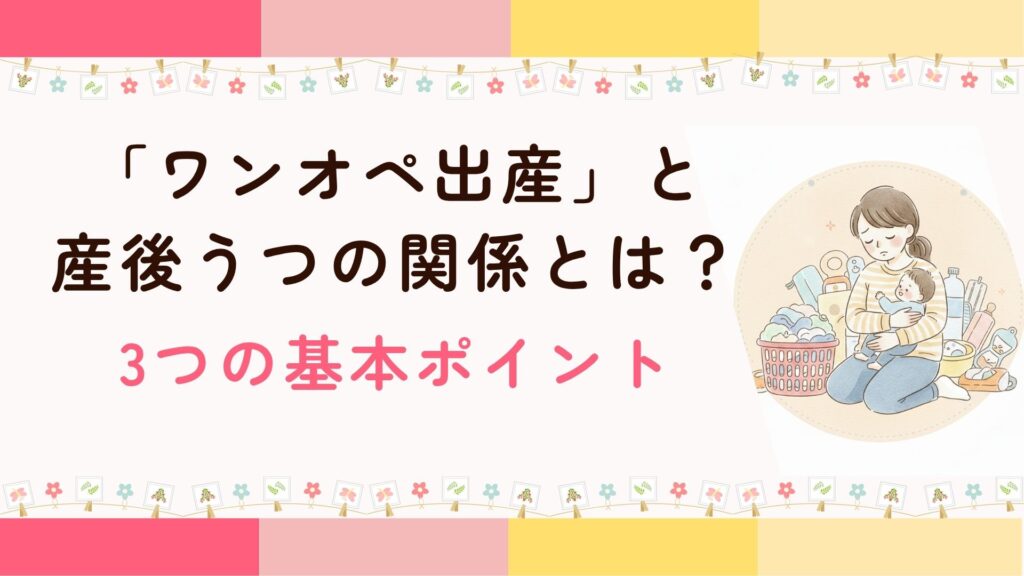
ひとりで出産・育児を抱えるワンオペ出産は、想像以上に心と体に負担がかかります。
実は、産後うつのきっかけになることもあるんです。
ここでは、「ワンオペ出産」と産後うつの関係を3つの基本ポイントをわかりやすく解説します。
- 「ワンオペ出産」は産後うつのリスクを高める可能性があることを理解しておく
- マタニティブルーと産後うつの違いを正しく理解しておく
- ワンオペ出産のママに現れやすい産後うつのサイン7つをチェックしておく
「ワンオペ出産」は産後うつのリスクを高める可能性があることを理解しておく
ワンオペ出産を経験したママは、産後うつのリスクを高める可能性をしっかり理解しておく必要があります。
なぜなら、出産という大きな出来事を支えてくれる人がいないと、孤独や不安、極度の疲れが重なってしまうから。
産後うつの傾向は、
- 出産直後、赤ちゃんが泣いても抱っこするのが怖くて涙が出た
- 退院後も家族のサポートがなく、夜中の授乳や夜泣きにひとりで対応している
- 「母親なんだから頑張らなきゃ」と自分を追い込み、涙が出て止まらなくなる

赤ちゃんが泣くのが怖いって思うのは、私が弱いだけなのかな?

それは違います。産後の心の不調は、気合いや根性では乗り越えられない環境の問題です。
少しでも「つらい」と感じたら、家族や友人、助産師さん、どこかに声を届けることが、笑顔を取り戻す第一歩になります。
マタニティブルーと産後うつの違いを正しく理解しておく
ワンオペ出産の「マタニティブルー」と「産後うつ」は、同じように見えて実はまったく違う心の状態であるという事を理解しておく事も重要です。
出産直後の不安定な気持ちは「マタニティブルー」かもしれません。
だけど、もしその落ち込みを2週間過ぎても引きずっている場合や、日常生活を送るのがつらいほどってなるなら、それは「産後うつ」の可能性があるんです。
具体的な違いはこんな感じ
- 期間の違い:マタニティブルーはだいたい出産後2週間以内におさまるけれど、産後うつは2週間以上続くことが多い。
- 症状の重さ:マタニティブルーでは涙もろい・気分の波などが中心。でも産後うつは、無気力・強い罪悪感・生活に支障が出るほどの落ち込みというような、深刻な状態が見られます。
- 対応の違い:マタニティブルーは多くが自然に回復しますが、産後うつは医療機関や専門家のサポートが必要なケースが少なくありません。

ホルモンバランスの乱れは誰にだってあるし、みんな泣いたり不安になったりしてるし、私もそのうち落ち着くかもって考えちゃって。

うーん。もし、2週間以上つらさが続いているなら、それは、ただの疲れじゃないかもしれません。
自分の心が出しているサインを、「気のせい」で終わらせないでくださいね。
「少し変だな」と感じたら、早めに周りや専門家に相談してみましょう。
心のケアは、赤ちゃんを守ることにもつながります。
ワンオペ出産のママに現れやすい産後うつのサイン7つをチェックしておく

「ワンオペ出産」のママに現れやすい産後うつのサインをチェックしておく事が大切です。
ワンオペ出産後は、身体の回復と同時に、赤ちゃんのお世話や家事がママ1人にのしかかるのに
1人で頑張り続けていると、自分では気づかないうちに産後うつのサインが出ているから。
具体的な、産後うつの主な症状は、
- 気分の沈み込みと涙
特別な理由もないのに涙が溢れてしまう、心が重く沈んでいる状態が続く。 - 意欲の低下・無関心
家事や育児に手がつけられず、「何もしたくない」という強い無気力感に襲われる。 - 睡眠パターンの乱れ
寝たいのに眠れない不眠、あるいは反対に、一日中布団から出たくないほどの過眠。 - 食欲の変化
食事が喉を通らない、またはストレスからか過食に走ってしまう。 - 感情の不安定さ
ちょっとした出来事にも関わらず、すぐに涙がこぼれてしまうほど感情が不安定になる。 - 赤ちゃんへの罪悪感
「可愛いのは分かっているのに、愛情を感じられない」と自分を責めて苦しくなる。 - 自己肯定感の低下
「自分なんて母親失格だ」と、自分自身を責め続ける気持ちが強くなり、どんどんネガティブな渦に陥ってしまう。

私がもっと強かったら、こんな風にならないんじゃないかな。

ワンオペで出産も育児も抱えていたら、誰だってしんどくなるんだから、そんな風に思っては駄目。もし今、産後うつの症状に心当たりがあって少しでもつらいと感じたら、1人で抱え込まないでください。
家族や友人に話すだけでも、心がスッと軽くなることがあるんです。
だから、これからは「頑張らない勇気」も、少しずつ持っていきましょうね。
「ワンオペ出産」で産後うつになりやすい人の5つの特徴とチェックリスト
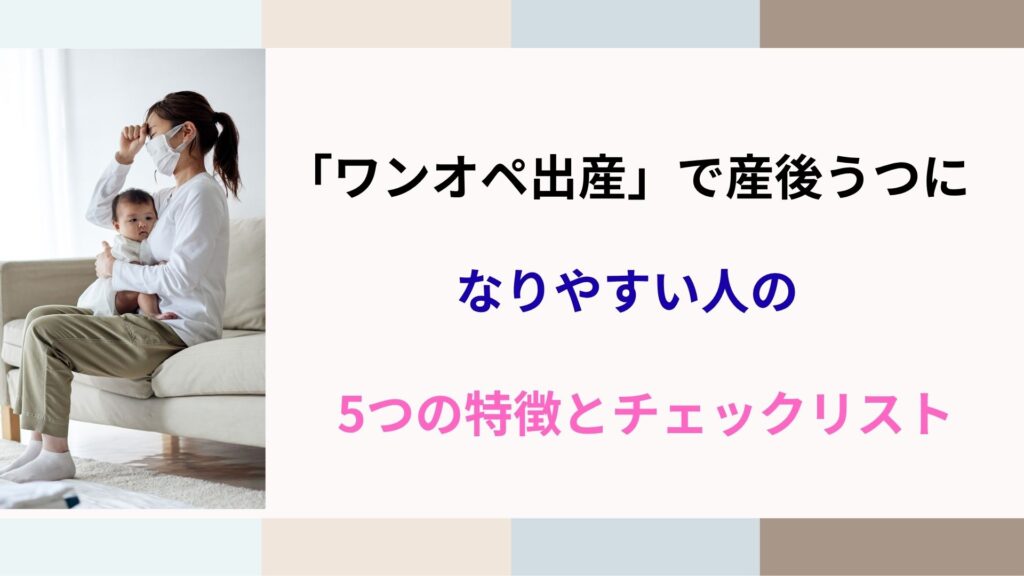
「ワンオペ出産」を経験したママは、知らず知らずのうちにキャパオーバーになってしまうことがあります。
とくにまじめで頑張りすぎるタイプや、人に頼るのが苦手な人は要注意。
ここでは、産後うつになりやすい人の特徴とチェックリストをわかりやすく紹介します。
- 「ワンオペ出産」で産後うつになりやすい人の特徴
- 「ワンオペ出産」ママの産後うつ セルフチェックリスト(はい/いいえで確認)
「ワンオペ出産」で産後うつになりやすい人の特徴
「ワンオペ出産」を経験したママの中でも、
真面目で責任感が強い人ほど、産後うつになりやすい傾向があります。
なぜなら、こうしたママは「ちゃんとしなきゃ」とか「母親なんだから頑張らないと」と、自分にプレッシャーをかけてしまうから。
たとえば、次のような特徴があるママは要注意。
- 真面目で責任感が強いタイプ
→「母親失格と思われたくない」といって、どんなに疲れても頑張りすぎてしまう。 - 完璧主義で手を抜けないタイプ
→育児も家事も100点を目指して「できない自分」に罪悪感を抱く。 - 人に頼るのが苦手なタイプ
→「迷惑をかけたくない」と1人で抱え込んで、限界まで我慢する。 - 孤立しやすい環境にいる人
→話を聞いてくれる人がいないから、不安や疲れが発散できない。 - 過去にうつ傾向や不安を感じた経験がある人
→ホルモン変化や睡眠不足で何度も繰り返しやすい。
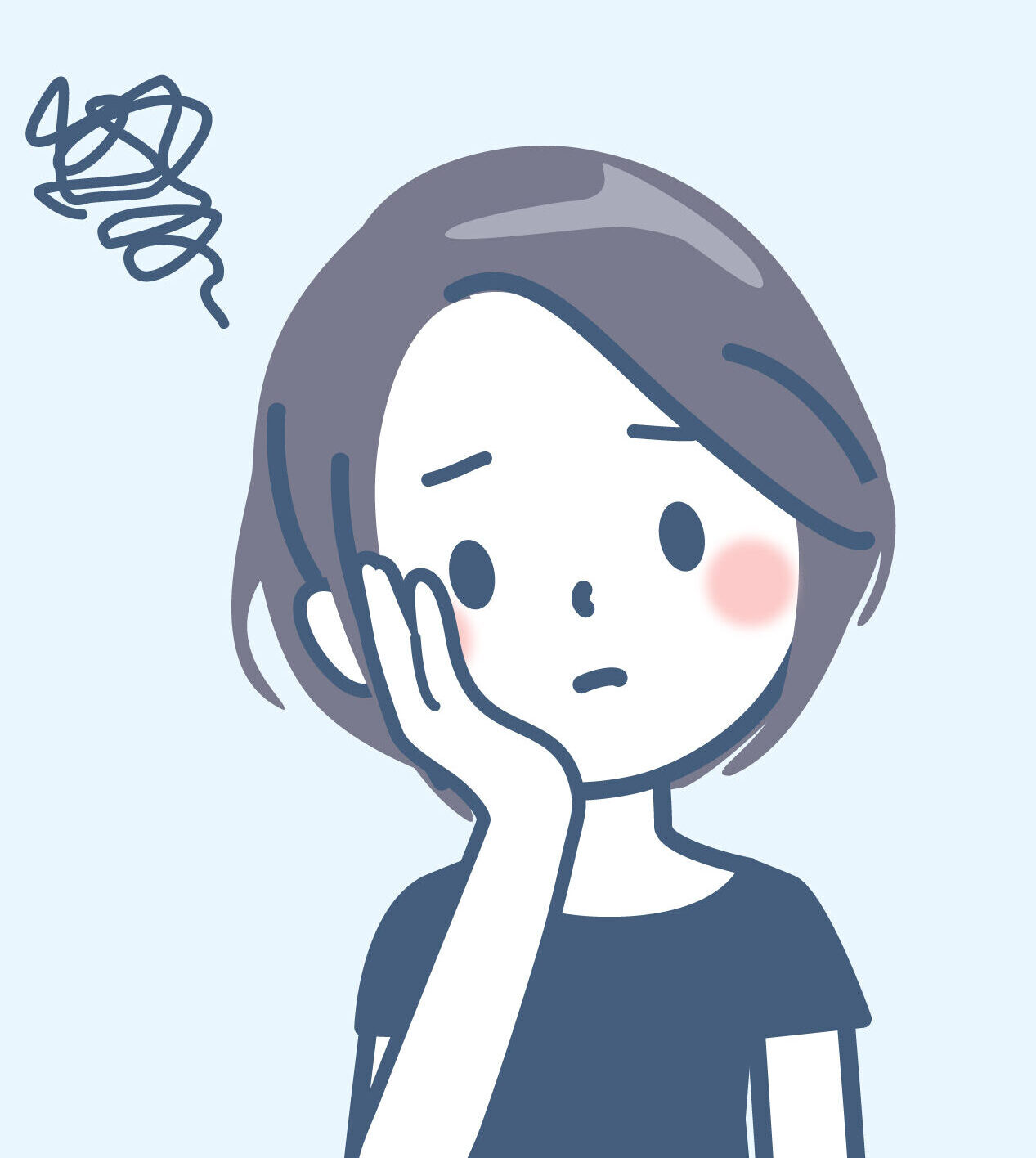
真面目に頑張るのは悪いことじゃないし、誰かに簡単に子どもを預けるなんてできないしな…。

私もそう思っていた時期がありました。でもね、「頑張ること」と「1人で抱え込むこと」は別物。
まずは「できない日があってもいい」「人に頼っていい」と認めること!
産後のあなたは、もう十分頑張っています。少し肩の力を抜いて、自分にも優しくしてあげましょう。
「ワンオペ出産」ママの産後うつ セルフチェックリスト(はい/いいえで確認)
ワンオペ出産ママのその辛さは、単なる疲れではないかもしれません。
心の状態を知るために、産後うつのセルフチェックをやってみましょう。
ワンオペ出産を乗り越えて、その後も頑張り続けていることで、心身が疲れきって、産後うつの状態に陥っていることに、自分ではなかなか気づけないから。
下の項目に「はい」がいくつ当てはまるか、チェックしてみてください。
□ 理由もなく涙が出る、または気持ちが重く沈んだ状態が2週間以上続いている
□ 家事や育児に手がつけられず、「何もしたくない」という無気力感が強い
□寝たいのに眠れない不眠、または反対に過剰に眠ってしまう日が続いている
□ 食欲がない、またはストレスでつい食べ過ぎてしまうなど、食生活が乱れている
□赤ちゃんを可愛いと思えず、「愛情を感じられない」と自分を責めて苦しくなる
□「自分は母親失格だ」と、自己肯定感が著しく低下している
□些細なことでイライラしたり、急に涙がこぼれるなど感情が不安定である
もし、このチェックリストで「はい」が3つ以上ついた場合は、あなたの心が悲鳴をあげているサインです。すぐに専門家のサポートが必要な状態かもしれません。

これぐらいならそんなに大したことじゃないから大丈夫。

そう思っているのが一番危ない!
もし当てはまる項目が多かったら、早めに専門機関や地域の相談窓口に頼ってOK。
話すだけでも気持ちが軽くなりますし、必要なサポートにつながります。
「自分の心を守ること」も、立派な子育ての一歩ですよ。
「ワンオペ出産」でどん底に…産後うつを乗り越えた3人のママの体験談

ここでは、産後うつを実際に乗り越えた3人のママの体験談と、心が軽くなるヒントをご紹介します。
「私だけじゃない」とホッとできるはず。
- 「ワンオペ出産」ママのリアルな産後うつ症状
- 「ワンオペ出産」ママの産後うつからの回復までの道のり
- 「ワンオペ出産」ママの産後うつを乗り越えて得た気づき
「泣いている赤ちゃんを抱けなかった」Aさんの話

ワンオペ出産を経験して産後うつの症状が出たAさんは「泣いている赤ちゃんを抱けなかった」と話しています。
出産後すぐに夫の単身赴任が決まり、Aさんはワンオペ状態での育児をスタート。
夜中の授乳、泣き止まない赤ちゃん、休む間もない家事で自分自身も相当疲れ切っていたんです。
Aママさんの話。
夜中2時。
泣きじゃくる赤ちゃんの声が部屋中に響いてて
私はベッドの端に座り、ぼんやりと我が子の泣き声を聞いていました。
抱き上げなきゃ、分かってるんだけど。
でも、やっぱり体が動かないし、重い。
頭では理解しているのに、心も体も凍りついたように動けなかった。
「母親なのに…ほんとにごめんね」と自分を責める気持ちが一気にあふれ、涙が止まらなくなりました。

我が子の泣き声が辛いって、私が弱いだけなのかな。

そんなことはありません。
1人で頑張る環境では、誰だって心が疲れるのは当然のこと。
泣きたいときは泣いていいし、周りや専門機関に相談することが、笑顔を取り戻す第一歩です。
「診断を受けて、やっと“自分を責めなくていい”と思えた」Bさんの話
ワンオペ出産ママのBさんは、診断を受けたことで初めて、「自分を責めなくてもいいんだ」と気づきました。
「みんな頑張ってるのに、私だけがダメなんだ。もっと頑張らなきゃ」と思い込んでいたBさん。その頑張りが、心を追い詰める原因に。
Bママさんの話
ある日、スーパーで。赤ちゃんが突然泣き出し、私は必死にあやそうとしました。
でも周りの視線が怖くて、手が震え、息が浅くなり、心臓がバクバクして止まらなくなって。
どうしようもならなくて、レジ前で立ち尽くしていたら、店員さんが「大丈夫ですか?」と声をかけてくれた瞬間、涙が溢れました。
そのまま外に出て、ベンチで泣きながら赤ちゃんを抱きしめ、初めて「もう無理かもしれない」と感じ診察を受けることに。
医師の「これは産後うつです。あなたが弱いわけじゃない。」という言葉に、胸の奥で何かがほどけるような感覚でホッとしました。

そうはいっても、子育ては自分がやることだし。

そうはいっても、無理に1人で頑張る必要はありません。
診断→カウンセリング→家族の理解→支援サービスの活用、というステップを少しずつ進めるだけで、必ず回復への道は開けます。
「ひとりじゃない」と思えることが、笑顔を取り戻す第一歩です。
「頼ることは負けじゃない」Cさんの話
Cさんは、出産後ずっと自分の疲れを騙し騙し家事と育児をこなしていました。
でも限界を感じて家族に相談したことで「頼ることは負けじゃない」と気付けたと言います。
だって、人に頼ること、少し手を抜く事で、自分を守る力が戻ってくる事が理解できたから。
Cママさんの場合は、
出産も退院後もずっと1人で、「母親なんだから頑張らなきゃ」って気を張ってました。
でも夜中に泣く赤ちゃんを前に、自分も泣いてしまって…。
思い切って夫に『もう無理』って言ったら「今までありがと」って抱きしめてくれて、涙が止まりませんでした。
あの瞬間、頼っていいんだって心から思えたんです。

ずっと1人で頑張ってたから、今更人に頼る事なんて出来ないよ。

そう感じるママもきっと多いですよね。
でも、頼ることは負けじゃなくて、自分と家族を守る勇気なんです。
「ワンオペ出産」は確かに大変な経験だけど、その中で見つけた気づきは一生ものです。
「ワンオペ出産」中のママのための5つの乗り越え方
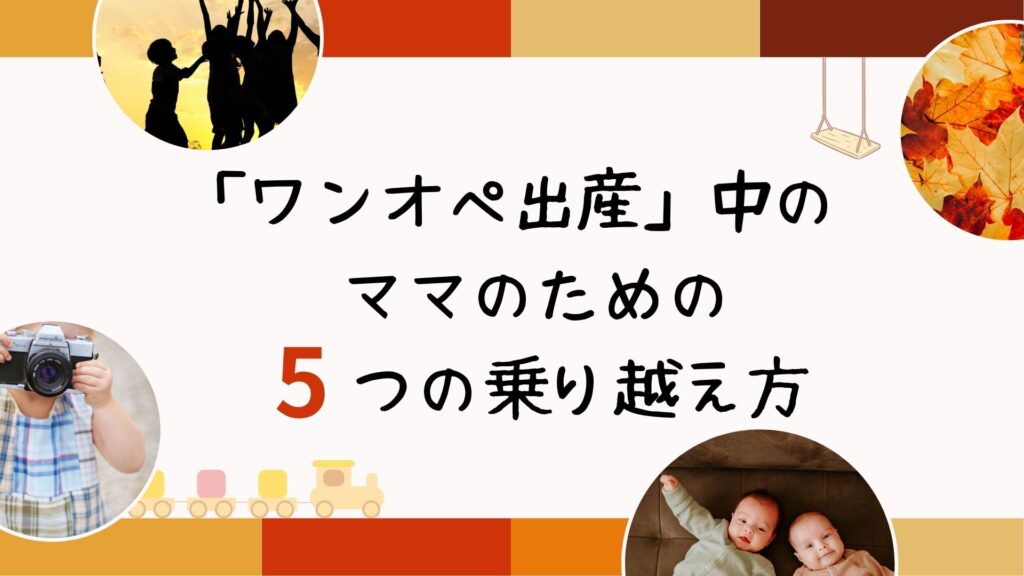
「ワンオペ出産」は、心も体も休まる時間がなく、孤独を感じやすいものです。
でも、少しの工夫やサポートで、そのつらさを軽くすることはできます。
こちらでは「ワンオペ出産」中のママが前を向くための5つの乗り越え方を紹介します。
- 専門家へ相談をする
- 家族や夫に「助けて」と伝える
- 自分をケアする時間を持つ
- 完璧主義を手放すこと
- 産後ケアサービスを活用すること
①専門家へ相談をする
「ワンオペ出産」をしているママがつらさを感じたとき、1人で抱え込まず専門家に相談することが何より大切です。
なぜなら、産後の心と体はホルモンの変化や環境の影響を強く受けやすく、「気の持ちよう」では解決できないケースが多いから。
相談できる専門家でいうと
- 産婦人科・心療内科・精神科:気分の落ち込みや不眠など、体と心の両面から診てもらえる
- 保健センター:地域の保健師さんに無料で相談でき、訪問支援も受けられる場合がある
- 育児支援窓口(市役所など):ベビーシッターや一時保育、家事支援などの制度を案内してもらえる

いやー、そんな病院なんて行くほどでもないしなー。

どんな小さな不調でも、「ちょっと変かも」と感じたら、迷わず専門家に相談してOKです。
それが、あなたと赤ちゃんを守る最初の勇気ある一歩です。
②家族や夫に「助けて」と伝える
「ワンオペ出産」から抜け出すには、夫や家族に「助けて」を伝えることが欠かせません。
なぜなら、出産も育児もチーム戦だから。
ママが1人ですべてを抱え込むと、どんな人だって体も心も限界を迎えちゃう。
どういう風に伝えるかというと
- 「今日は10分だけでも寝たいから、赤ちゃん見ててもらえる?」
- 「オムツ替えお願い!その間に夕飯だけ準備するね」
- 「もう無理って言いたい日もある。でもあなたがいるから頑張れるよ」

頼んだときだけはやってくれるだろうけど、続くのかな…。

最初のうちは、何度か自分から伝えていかないといけないかもしれないけど
小さな「助けて」が積み重なれば、一緒に育てる関係に変わっていけます。
③自分をケアする時間を持つ
ワンオペで毎日がいっぱいなときほど、自分をケアする時間を少しでも持つことが大切です。
だって、ママの心が元気でないと、家庭全体のバランスも崩れてしまうから。
- 睡眠:5分でも目を閉じて休む
- 食事:おにぎり1つでも、きちんと食べる
- 気分転換:好きな音楽を聴いたり、アロマの香りで深呼吸

そんな時間なんてないし、自分の事なんて後回しだから結局やらないんだよね。

そうですよね。でもね、少し休む勇気が、明日の笑顔を作るんです。
しっかり休む事が出来なかったとしても、ママが息をつける瞬間があれば、それで十分です。
④完璧主義を手放すこと
ワンオペ出産を経験したママが完璧主義を手放すことは、心を守るために欠かせない大切なステップです。
だって、育児も家事も終わりがない仕事なのに、「ちゃんとやらなきゃ」とか「母親なんだから」って、自分を追い込んでしまうと、当たり前に心が疲れるから。
例えば、こう言う風に
夜泣きがひどい日でほとんど徹夜。
正直、自分のご飯なんてどうでもいいって感じだったけど、子どもはそうはいかない。
思い切ってレトルト離乳食を使った日、「あれ?子どもが笑ってる。私も少し笑えた」と気づいたんです。
それ以来、「ちゃんとやらなきゃ」よりも「笑顔でいられる方を選ぼう」に切り替えたら、気持ちがぐっと楽に。

分かってるけど、そんな簡単に割り切れたら苦労しないよ!

そうですよね。
でもね、今日はこれで十分って言える日が増えるほど、心の余裕も戻ってくるんです。ほどほどでいい、笑顔でいることが一番大事。
そう思えたとき、ママの心はぐっと軽くなりますよ。
⑤産後ケアサービスを活用すること
ワンオペ出産の負担を軽くするためには、地域の産後ケアサービスを遠慮せず使うことが大切。
だって、産後ケアサービスは、ママと赤ちゃんを守るための仕組みなんだから。
遠慮なく使わなきゃもったいない!
産後ケアサービスの使い方イメージはこんな感じ。
- 家事代行サービスを利用し、洗濯や掃除を任せることで、ママは休息やリフレッシュの時間を確保。
- ベビーシッターに短時間預けて、美容院や買い物など「自分のための時間」を過ごす。
- 産後ケア施設で助産師のサポートを受けながら、心身の回復に専念。
- ファミリーサポートセンターに登録し、地域のママ同士で子育てを支え合う。
- 自治体の育児ヘルパーや子育て支援センターを活用して、気軽に相談や一時保育を利用。

えぇー!こんなに使っていいの?それにお金もかかるよね。

それが今の時代の子育ての形なんです。もちろん「お金がかかるし、気が引ける…」と感じる人も多いでしょう。
でも、行政の補助金や助成制度が使えるケースもあります。
まずは市役所や保健センターに相談してみてくださいね。
「ワンオペ出産」で悩まないようにするため、パートナーや家族に知っておいてもらうべき3つのこと
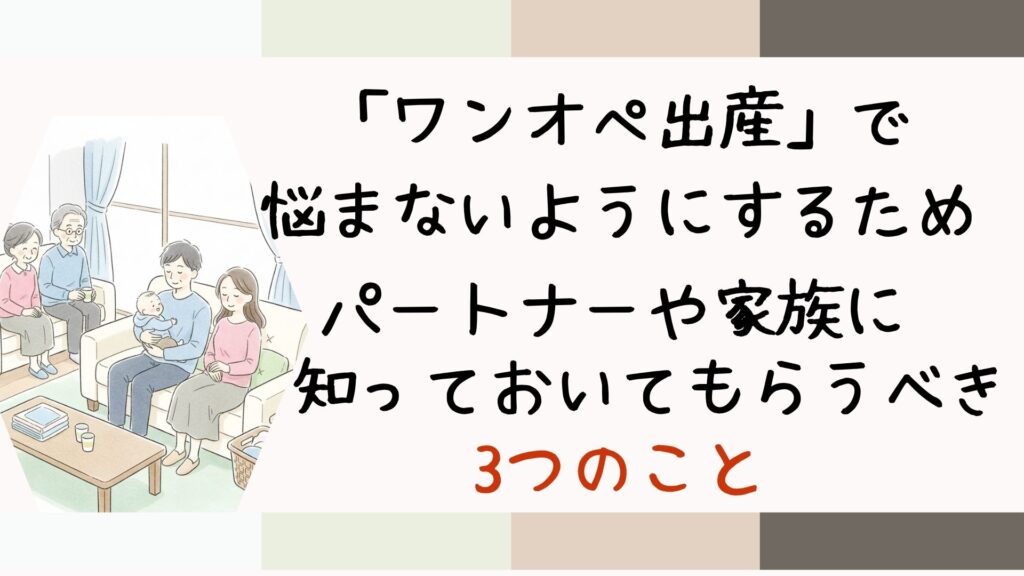
「ワンオペ出産」で悩むママを支えるために、パートナーや家族に知っておいてもらう3つのポイントをわかりやすく解説します。
ママの心に寄り添い、笑顔を取り戻すための小さな一歩を、一緒に見つけていきましょう。
パートナーや家族に知っておいてもらうべき3つのこと
- 「ワンオペ出産」ママの産後うつの理解してもらうこと
- 「ワンオペ出産」ママへ共感してもらうこと
- 「ワンオペ出産」ママのために行動してもらうこと
「ワンオペ出産」ママの産後うつの理解してもらうこと
「ワンオペ出産」ママの産後うつは、心の弱さや努力不足ではなく、誰にでも起こりうる自然な反応なんだと理解してもらうことがとても大事です。
出産と育児をほぼ1人で乗り越えると、睡眠不足や疲労がたまるし、ホルモンの変化だってあるんだから、心のバランスが崩れるのは当たり前。
理解の仕方は色々あって
- 医師監修の記事や自治体のリーフレットを読んで、**産後うつは「心の弱さ」ではなくホルモンや環境の変化による病気だと学ぶ。
- 「ママの気持ちの問題かな?」ではなくて、医学的な視点で理解しようとする姿勢を持つ。
- ママが泣いていたりイライラしても、「ママが怒ってる」ではなく、SOSのサインかもしれないと受け止める。
- ワンオペ出産は孤独・不安・責任感のプレッシャーを感じて当然と考える。
- SNSなどで「ワンオペ出産」経験者の体験談を読んで、リアルな気持ちを知る。
- 「休めばいいんじゃない?」「後ででもいいよ」ではなくてどうすれば少しでも気が楽になる?と一緒に考える姿勢を持つ。

ちょっとした気持ちの落ち込みでしょ?って思っちゃうんじゃないかな。

そう思う人もいるかもしれません。でも、ワンオペ出産の状況では、これは自然な反応です。まずは病気として理解することが大事です。「頑張れ」と言うより、「大変だったね」と受け止めるだけで、ママの心は少し軽くなります。
「ワンオペ出産」ママへ共感してもらうこと

「ワンオペ出産」ママには、パートナーや家族からの共感の言葉や態度が何より心の支えになります。
1人で頑張るママは孤独感や不安が大きくなってるから、誰かに理解されるだけで安心感が生まれる。
例えば、
- 「夜泣き、本当に大変だよね」と声をかける
- 「頑張ってるね、偉いね」と認める
- ただそばに座って話を聞く

何もできないのに話を聞くだけでいいの?って言われそう。

聞くだけで心が軽くなることは多いのです。そして、共感するだけでもママの負担は減ります。まずは否定せず、ありのままを受け止めることが第一歩です。
「ワンオペ出産」ママのために行動してもらうこと

「ワンオペ出産」ママにとっては、具体的に行動してもらえることが重要なんです。
だって、言葉だけだと信憑性が低いし、行動で助けることが一番ママの心と体を守れるから。
家事や育児の分担、休息時間の確保など環境を変える行動だけで全然違う!
どういう行動かというと
- 夜は交代で授乳やおむつ替えを担当する
- 家事を代わりにやって、ママが休める時間を作る
- 気になる症状があれば、専門機関への受診をサポートする

さすがに全部はできないし、出来るか不安。

やらないよりかは全然マシ!小さな行動でもママの心を大きく軽くできるのです。迷わず、できることから始めましょう。
まとめ : 「ワンオペ出産」から一歩踏み出して笑顔を取り戻そう
「ワンオペ出産」は、心も体も限界を感じやすい状況です。
頼れる人がいないまま出産や育児を抱え込むと、気づかないうちに心が疲弊してしまうのは当たり前。
あなたは決して1人じゃありません。
産婦人科医や保健センター、地域の育児支援、家族やパートナーなど、あなたを支える窓口や人は必ずいます。
「ちゃんとしなきゃ」とか「私が頑張らないと」と思う気持ちは本当に立派。
だけど、その頑張りが行きすぎると、自分を追い詰めてしまうこともあるんです。
そんなときは、
- できない日があっても自分を責めない
- 「助けて」を言う勇気を持つ
- ほんの少しでも自分をいたわる時間を作る
この3つを思い出してください。
それだけで、あなたの心に少しずつ光が戻ってきます。
まずはあなた自身が心地よく過ごせるように、少しずつ、無理のないペースで前に進んでいきましょう。
まずは、「ワンオペ出産」と産後うつの関係とは?3つの基本ポイントを解説。
- 「ワンオペ出産」は産後うつのリスクを高める可能性があることを理解しておく
- マタニティブルーと産後うつの違いを正しく理解しておく
- ワンオペ出産のママに現れやすい産後うつのサイン7つをチェックしておく
次に、「ワンオペ出産」で産後うつになりやすい人の5つの特徴とチェックリストを紹介。
- 「ワンオペ出産」で産後うつになりやすい人の特徴
- 「ワンオペ出産」ママの産後うつ セルフチェックリスト(はい/いいえで確認)
そして、「ワンオペ出産」でどん底に…産後うつを乗り越えた3人のママの体験談
- 「ワンオペ出産」ママのリアルな産後うつ症状
- 「ワンオペ出産」ママの産後うつからの回復までの道のり
- 「ワンオペ出産」ママの産後うつを乗り越えて得た気づき
さらに、「ワンオペ出産」中のママのための5つの乗り越え方を解説。
- 専門家へ相談をする
- 家族や夫に「助けて」と伝える
- 自分をケアする時間を持つ
- 完璧主義を手放すこと
- 産後ケアサービスを活用すること
最後に、「ワンオペ出産」で悩まないようにするため パートナーや家族に知っておいてもらうべき3つのこと
パートナーや家族に知っておいてもらうべき3つのこと
- 「ワンオペ出産」ママの産後うつの理解してもらうこと
- 「ワンオペ出産」ママへ共感してもらうこと
- 「ワンオペ出産」ママのために行動してもらうこと
ワンオペで毎日ヘトヘトになっているのに、
私が頑張れば大丈夫って思い込んでいませんか?
実は、ワンオペ育児の辛さを解決するのは、才能や根性の問題じゃありません。
「プロに頼って負担を減らしているかどうか」
たったそれだけで、育児は、地獄にも楽しい時間にも180度変わるんです。
私もかつては、家事も育児も全部背負ってボロボロ…。
そんな私を救ってくれたのが宅配食でした。
そこからは本当に驚くほど育児が楽になり、
子どもと笑って過ごせる余裕がある私に変わったんです。
あなたも、頑張らなくてもいいワンオペ育児を体感してみませんか?
⇒宅配食で笑顔を取り戻した私のワンオペ育児物語ワンオペ育児物語より、まずは、おすすめの幼児向けの宅配食を知りたいというあなたには、こちらの記事がおすすめ。
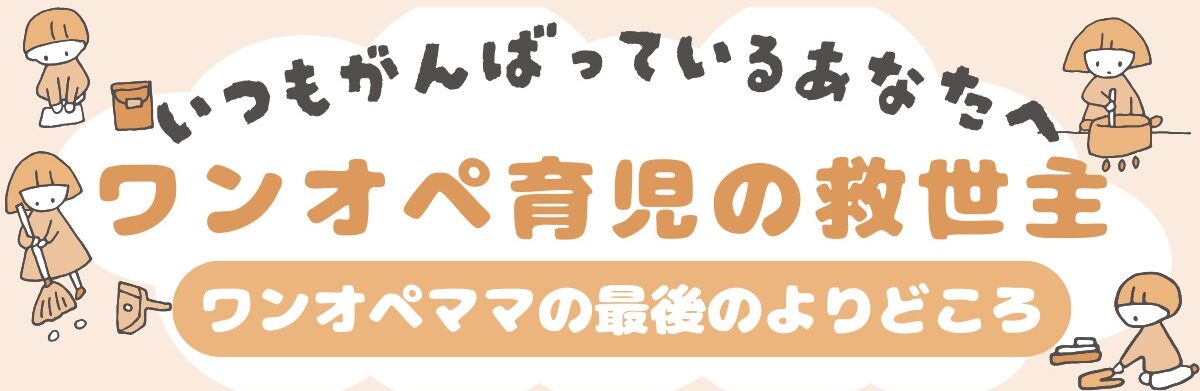
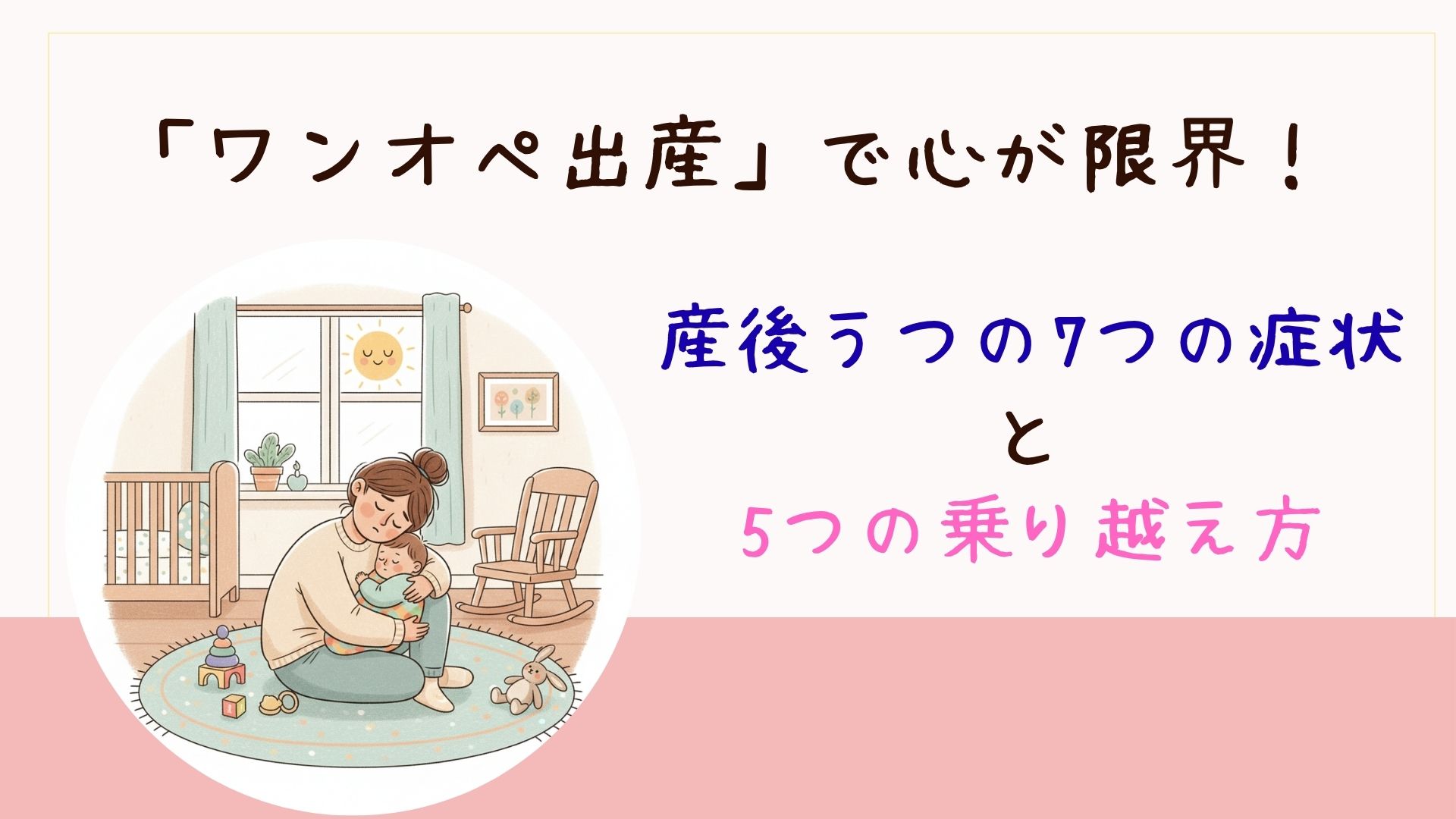

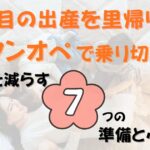

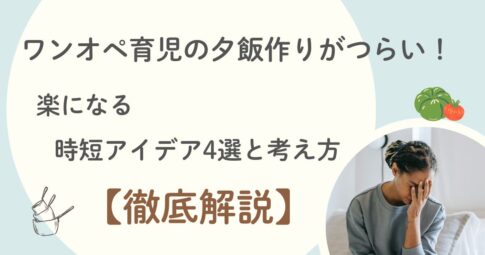

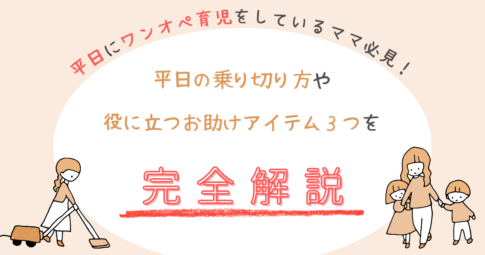
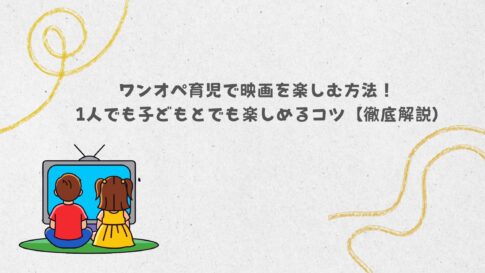
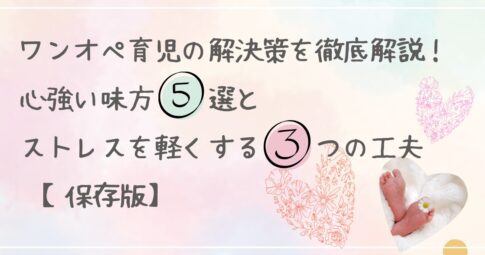
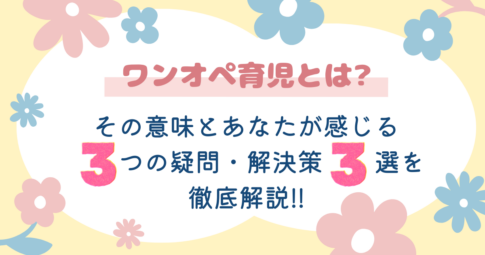
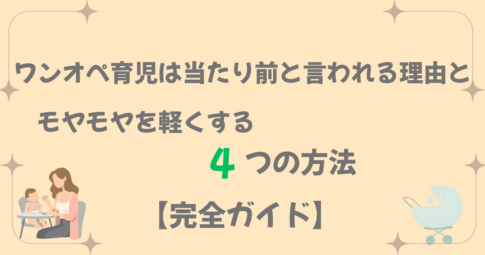



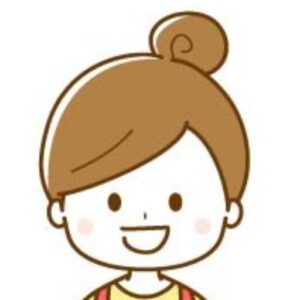
1歳と3歳の怪獣兄弟を育てる、絶賛ワンオペ育児中のまやです。
かつては、家事も育児も全部自分でやらなきゃと気合と根性だけで挑み、
気づけば毎日ヘトヘト、イライラ、そして自己嫌悪…。
でも今は、違います。「頼れるものは、頼っていいんだ!」
それを知ってから、ワンオペ育児がぐっと楽に、むしろ楽しくなりました。
詳細なプロフィールはこちら